電子帳簿保存法の改正が予定されています。改正では、紙保存だけでOKだった一時的な措置が終了することのアナウンスがありました。その代わり、猶予措置が予定されています。
この猶予措置の適用を受けるときには、「相当の理由」が必要です。今回は、この相当の理由がなにかを考えていきます。
宥恕措置から猶予措置へ
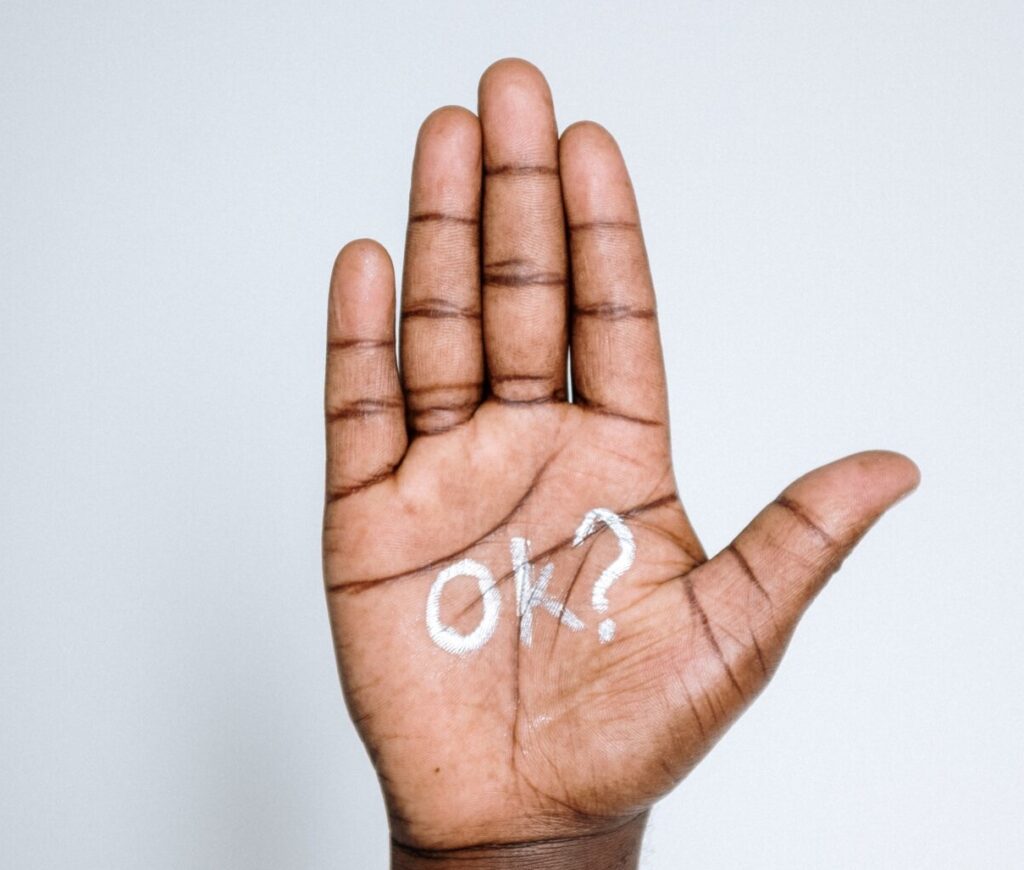
2022年と2023年の間は、電子帳簿保存法に対応しなくても、許されていました。これが、いわゆる宥恕措置といいます。名前が分かりにくいのですが、「とりあえず、対応しなくても待ちますよ」という内容です。
これが2023年12月31日で切れることが確認されました。
その代わり、「データを保存するなら紙の保存を続けてもいいですよ」という猶予措置ができる予定です。しかしながら、猶予措置の適用を受けるときには、「相当の理由」が必要です。
相当の理由とはなんでしょうか?
やむを得ない理由から相当の理由へ

相当の理由の内容は、はっきりしていません。しかし言葉の厳しさを考えてみましょう。
これまでは、「やむを得ない理由」です。「やむを得ない」ということは、「本当は対応したいのだけれどもやむにやまれない理由があってできません。」という意味です。
これに対して、「相当の理由」であれば、やむを得ない必要はないのです。やむにやまれない理由がなくても、なにかしらの理由がれば認められると考えられます。
具体的な内容ははっきりしていません。
相当の理由の趣旨は広く優しくするため

「相当の理由」に該当するだろうと言われている例示を見ていきましょう。
予想されるもの
- 人材が間に合わなくて対応ができない
- ソフトウェアの導入が間に合わない
この辺りです。
届け出が必要なわけでもなく、承認が必要なわけでもなさそうです。
ということは、とりあえず理由がありますよと言えば、猶予措置が適用できるだろうということです。
もちろん、これは暫定の解釈なので正式な発表は確認をしてください。
ほとんどの人が適用されると考えていい
上記の通りで「相当の理由」は、ほとんどの人が適用されると考えて大丈夫でしょう。あとは、それを適用するのか、経営として一番適切な選択肢かを考えましょう。
国税庁は、様々な人に対応することを目的としている
納税者側からすると、国税庁や税務署は取り締まる側です。だから、なんとなく厳しい対応をするのだろう、締め付けるのだろうと考えるかもしれません。
しかし、今回の電子帳簿保存法は、すべての事業者が関係しています。あまり厳しい条件にすると守れない人が続出することが予想されます。また、この記事を読んでいる方は大丈夫でしょうが、世の中を広く見ると、事業をしているけれどもまったく帳簿付けしていない人や、電子機器を全く使わないで処理をしている人も存在するのです。
そういった、あまねく人に対応することを念頭に制度が緩まっているのが現状です。きちんと対応準備は必要ですが、適用当初もそこまで厳しくならない可能性はあるでしょう。もちろん、税務調査時で追徴課税される危険性も念頭に置くべき点です。
正式な発表は2023年6月くらいだろう
なお、今回の改正に伴って、国税庁の説明文書が出てくると考えられます。通達も同様です。国税庁の説明文書が出てくるのは2023年6月くらいかと考えれます。
いつ情報が出てくるか待っている人は、2023年6月くらいにもう一度確認してみましょう。l
しっかりと準備を進めよう
原則的な対応をする場合は、これらの通達や説明文書はあまり関係がないです。法律としては、おおよそ出ていますので、現状でも対策可能です。
これから対策を進めたい個人事業主や中小企業の方もいるでしょう。そういった方向けに、無料のWEBセミナーの開催を予定しています。お時間が合えば、ぜひご参加ください。
2023年8月の一問一答での補足
電子帳簿保存法の一問一答において補足があります。
引用は確認のために載せておきますが、分かりにくいかもしれませんので、補足も入れておきます。
相当の理由は何になるかということです。環境が整うまでは、システム、組織、資金、人手などの理由で認められるということです。この理解で大丈夫です。
このあたりは客観的な理由を付けるのが難しい気はします。どうやって証明するのか分かりません。数値などもありませんので、一応の妥協として決められるのでしょう。「ただし、」以降は、余裕があるのに適応して逃れる場合をなくすためと考えられます。
- 61… どのような場合がここでいう相当の理由があると認められることとなりますか。
その電磁的記録そのものの保存は可能であるものの、保存時に満たすべき要件に従って保存するためのシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等といった、自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含め、要件に従って電磁的記録の保存を行うための環境が整っていない事情がある場合については、この猶予措置における「相当の理由」があると認められ、保存時に満たすべき要件に従って保存できる環境が整うまでは、そうした保存時に満たすべき要件が不要となります。
ただし、システム等や社内のワークフローの整備が整っており、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存時に満たすべき要件に従って保存できるにもかかわらず、資金繰りや人手不足等の理由がなく、そうした要件に従って電磁的記録を保存していない場合には、この猶予措置の適用は受けられないことになります(取扱通達7-12)。
また、猶予措置を書類廃棄の理由にしないようにということがあります。もともと、書面も提示しないと猶予措置は受けられませんので、どういう質問の意図か測りかねます。色々な質問があります。
- 64 令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、検索機能の確保の要件が不要とされる「電磁的記録を出力した書面であって、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものの提示若しくは提出の要求に応じることができる」ようにして保存していましたが、書類の保存スペースの関係から、電磁的記録を出力した書面を廃棄して電子データのみを保存することを検討しています。この場合は、税務署長が「要件に従って保存することができなかったことについて相当の理由がある」と認めた場合に該当して規則第4条第3項の規定の適用はありますか。
…その要件を満たすことができなくなった場合については、「要件に従って保存することができなかったことについて相当の理由がある」と認められません…
原則にしても、特例にしてもやり方はございます。
必要なソフトウェアのご紹介も可能ですので、気になる方はお問い合わせください。





